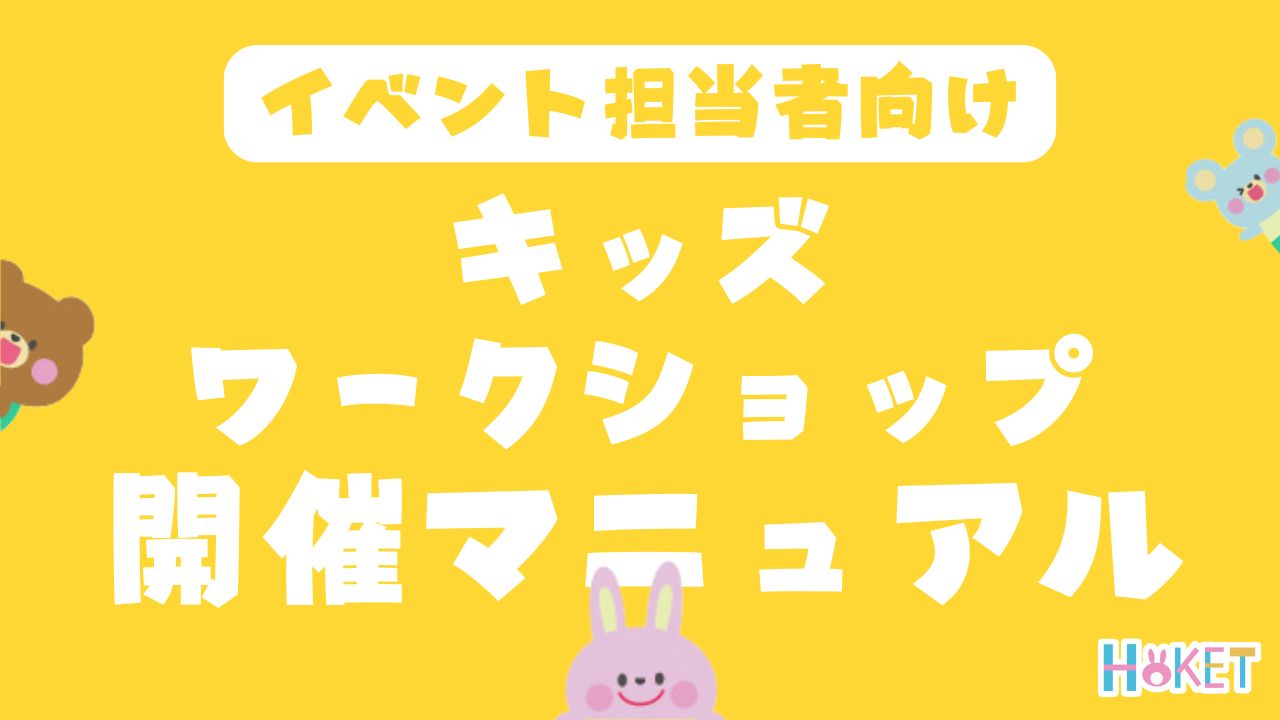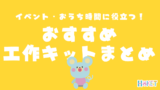「子ども向けのワークショップを企画することになったけれど、どこから手をつけていいかわからない…」
そんなお悩みを抱えている方に向けて、この記事では初めてでも失敗しないワークショップの企画・運営方法を、HOKETの豊富な実績をもとにわかりやすくご紹介します。
この記事はこんな方におすすめです
- 子ども向けイベントを初めて担当する企業のご担当者さま
- 集客・広報・販促施策として親子イベントを企画しているマーケティングご担当者さま
- 子どもと一緒にイベントを楽しみたい保護者や教育関係者の方
企業イベント、商業施設、地域行事など、どんなシーンでも活用できるアイデアと運営ノウハウを詰め込みました。
さらに、企画〜運営までまるごと任せられる「HOKET LAB」の活用方法もあわせて解説しています。
「楽しくて、記憶に残る体験を子どもたちに届けたい」
その思いを“カタチ”にするヒントを、この記事で見つけてください。
まずはここから!ワークショップ開催の3つの方法
子ども向けワークショップを成功させるには、目的やリソースに応じて、適切な開催スタイルを選ぶことが大切です。
以下の3つの方法を比較しながら、自社やチームの状況に合った方法を選びましょう。
1. 自分で企画・開催する(DIY型)
ワークショップの企画から準備、当日の運営までをすべて自社で担当する方法です。
メリット
- 自由度が高く、オリジナルの企画を実現しやすい
- コストを抑えやすい(外注費不要)
注意点
- 内容設計や安全対策に専門知識が必要
- スタッフの負担が大きくなることも
こんな方におすすめ
- 少人数・小規模で実施したい
- 社内にイベント経験者がいる
2. 専門業者に委託する(プロサポート型)
企画・準備・運営をイベント専門業者に依頼する方法です。
初めての担当でも安心して任せられるのが大きな魅力です。
メリット
- 企画提案から運営まで一括対応
- 品質や安全性の担保がしやすい
- イベント担当者の工数を大幅削減
注意点
- 外注費がかかる
- 内容によっては事前打ち合わせが必要
業者選定時のチェックポイント
- 子ども向けイベントの実績が豊富か
- 柔軟な対応(カスタマイズなど)が可能か
3. ワークショップ用キットを使う(ハイブリッド型)
工作キットなどの完成された教材を活用して開催する方法です。
「自分で開催したいけど、準備の手間は減らしたい」という場合に最適です。
メリット
- 材料や説明書がセットになっているため準備が簡単
- 内容のクオリティを一定に保てる
- 自由度と効率性のバランスが良い
注意点
- キットの内容や数量に注意(在庫確認・予備手配)
- 進行は自分たちで行う必要あり
おすすめの選び方
- 安全基準を満たしている製品
- 口コミ評価が高いショップを選ぶ
- レクチャー動画などが付属していると安心
下記の記事で市販されているおすすめの工作キットも紹介しています。
開催方法の比較表
| 項目 | 自社開催 | 業者委託(HOKET LABなど) | キット活用 |
|---|---|---|---|
| 準備の手間 | 多い | 少ない | 中 |
| 自由度 | 高い | 中〜高(カスタム可) | 低い |
| 費用感 | 低い | 中〜高 | 中 |
| クオリティ・安全性 | 担保が難しい | 高い(プロ対応) | 一定水準あり |
| 初めての担当に向いてる? | △ | ◎ | ◯ |
企画の自由度を重視したいか、効率や安心感を優先したいかで、最適な方法は変わります。
子ども向けワークショップ企画の基本ステップ
子ども向けワークショップを成功させるためには、企画段階での準備と設計が最も重要です。
ここでは、HOKETが企業・団体向けに実践している「基本の5ステップ」をご紹介します。
1. テーマとターゲットを明確にする
ワークショップのテーマ選びは、参加者の満足度を大きく左右します。
テーマ設定のポイント
- 年齢・興味関心・季節性・地域性を意識
- 夏休み → 自由研究を兼ねた工作や実験系
- 秋 → ハロウィンなどイベントに連動
- 商業施設 → SNS映えする装飾・写真スポット系
- 保育施設 → 短時間で終わる安全な体験系
- 時間→年齢に応じた時間設定
対象年齢の設定
対象年齢によって、必要なサポート体制や内容の難易度も大きく変わります。
- 未就学児:道具の安全性や保護者同伴を想定
- 小学生:自由研究や「考える楽しさ」を含めた構成に
2. イベントの目的と「成功の定義」を決める
企画段階で「このイベントは何のために行うのか?」という目的を明確にし、
それに対する成功の指標(KPI)を設定しておくことで、運営方針がブレずに済みます。
目的設定の例
- 学びの提供:科学実験やエコ活動など、楽しく学べるテーマ
- 発想力の育成:自由な工作・アート体験で表現力を伸ばす
- チームワーク促進:親子やグループでの協力作業による一体感
成功の基準(KPI)例
- 満足度アンケートで「楽しかった」回答が80%以上
- 子ども全員が作品を完成
- SNSへの投稿数や参加者数の目標達成
- 保護者やクライアントからの好評価・継続依頼
3. 予算を見積もり、適正な費用設定をする
子ども向けワークショップの開催方法にかかわらず、予算の把握と事前の見通しはとても大切です。
ここでは、外部委託する場合と自社で開催する場合の、それぞれの予算設計の考え方をご紹介します。
外部業者に依頼する場合の例
企画〜運営を外部に委託する場合は、使える予算額の上限を明確にしたうえで相談することが成功のカギです。
- 最初に「目安の参加人数」と「想定している費用感」を伝えるとスムーズです
- 会場費は主催者側で確保し、運営だけを依頼する形も可能です
- 見積書などを資料として提供可能な業者を選ぶと安心です
自社で開催する場合の費用イメージ
すべて自社で準備・開催する場合には、下記のような項目ごとにコストを試算しましょう。
| 費用項目 | 内容例 |
|---|---|
| 材料費 | 例:1人あたり500円の工作キット材料など |
| 会場費 | 公民館や施設のレンタル費(例:5,000円/日) |
| 備品・道具 | ハサミ、のり、机、パネルなど(レンタル可) |
| スタッフ人件費 | 例: 3人 × 6時間 |
| 安全対策費 | 消毒・保険・救急用品など |
| 予備費 | 材料不足やトラブル時の対応費用 |
コストを抑える工夫(自社開催時)
- 高価な備品はレンタルで対応(机・椅子・音響など)
- ワークショップ内容を「1種類×複数回転」式にすることで材料のロス削減
4. スケジュールを立てる(準備〜当日)
スムーズな運営には、当日だけでなく事前準備から逆算したスケジュール設計が必要です。
🗓 スケジュール例
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 10:00〜11:00 | 準備(材料セット、机配置) |
| 11:00〜17:00 | ワークショップ本番 |
| 17:00〜18:00 | 片付け・忘れ物確認・撤収 |
5. リスクマネジメントを事前に整える
イベントには必ず「想定外」が起こります。事前の備えが安全で信頼される運営につながります。
よくあるトラブルと備え
| トラブルの例 | 対応策 |
|---|---|
| 材料が足りない | 参加人数+αで準備/予備の道具を常備 |
| 悪天候で屋外イベント中止 | 室内スペースを確保/中止判断基準を事前共有 |
| 当日欠席者が多い | リマインドメール送付/当日飛び入り対応の仕組み |
| 子どものケガ・トラブル | 道具の選定に注意/救急セット常備/保険加入 |
| 保護者からのクレーム対応 | 案内表示の徹底/記録写真・対応ログの保存 |
下記記事で安全面に配慮した素材・道具選びのコツを紹介しています。
この5ステップをしっかり押さえることで、企画から当日運営までスムーズに進められる土台が整います。
ワークショップ内容の決め方とジャンル別アイデア
「どんな内容にすれば、子どもたちが楽しんでくれるだろう?」
ワークショップの内容(テーマ)選びは、イベント全体の印象を左右する最重要ポイントの一つです。
ここでは、HOKETが実際のイベントで反響の大きかったコンテンツをもとに、3つの定番ジャンル別にアイデアと実践ポイントをご紹介します。
1. ものづくり系ワークショップ(創造・達成感)
子どもたちが手を動かして形に残る体験ができる、定番ジャンル。
自由な発想を楽しめ、満足感も高く、参加者の記憶にも残りやすいのが特徴です。
代表的な内容例
- かわいい小物・アクセサリーづくり
- 再利用素材を使ったエコ工作
- デコレーションキャンドル・フォトフレーム制作
実践ポイント
- 小さい子どもでも扱える「安全な素材・道具」を選ぶ
- 年齢ごとのサポートレベルを分けておくと安心
- 完成までの所要時間を30〜60分以内に設定
実際の工作例
2. エンタメ系ワークショップ(遊び・盛り上がり)
「作るだけじゃ物足りない!」という子どもたちに大人気。
ゲーム性や体験要素を取り入れた内容は、イベント会場の雰囲気を盛り上げたい時に最適です。
代表的な内容例
- 紙コップで作るクレーンゲーム
- 的当てゲーム・宝探しアクティビティ
- 回して当てる工作ルーレット
実践ポイント
- シンプルな仕組みで年齢を問わず楽しめるものを選ぶ
- 「全員が成功体験を得られる」ルール設計を意識する
- 進行役が盛り上げやすい工夫を取り入れると◎
実際の工作・イベント例
3. 学び系ワークショップ(教育+体験)
保護者・教育関係者からの評価が特に高いジャンルです。
科学や環境、金融などをテーマに、「学び+体験」ができる設計がポイントです。
代表的な内容例
- 簡単な化学実験(色変化、泡、においなど)
- 環境に優しいクラフト(リサイクル・自然素材)
- お金の使い方を考えるミニショップ体験
実践ポイント
- 学習要素を入れつつ「楽しさ」優先の演出を
- 記録シートやワークブックを用意すると保護者の満足度アップ
- スタッフが説明しやすいように図解や資料を準備
実際の工作・イベント例
どれを選べばいい?テーマ選定のポイントまとめ
企画段階でイベントの目的を明確にして、それに合ったテーマを設定することがイベント成功の重要なポイントです。
| 優先したいこと | おすすめジャンル |
|---|---|
| たくさんの人を集客したい | ものづくり系 |
| 会場を盛り上げたい | エンタメ系 |
| 保護者や企業から評価されたい | 学び系(教育+SDGs) |
ワークショップ開催の準備と運営ノウハウ
企画が固まったら、いよいよ実施に向けた準備です。
会場選び・集客・決済・当日の運営設計まで、一貫した段取りが成功のカギになります。
1. 会場選びとスケジュール設計
会場選定のポイント
子ども向けワークショップでは、以下の点に配慮して会場を選びましょう。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 広さ・安全性 | 十分な作業スペースが確保できる/転倒・ケガの防止策が可能か |
| 設備 | 低い机、やわらかい床材、換気・空調など |
| アクセス | 公共交通機関/駐車場の有無、ベビーカー対応 |
| 導線設計 | 入退場の動線がスムーズか、保護者待機スペースの確保 |
| 屋外の場合 | 日よけ・雨対策/予備日設定の有無/室内代替案の検討 |
日程と時間帯の選び方
- ファミリー層が参加しやすい「午前〜昼過ぎ」がベスト
- 集中力の観点から「夜開催」は避ける
- 商業施設などでは「来店ピーク時間帯」に合わせると効果的
2. 告知と参加者募集
効果的な告知手段
| 手段 | ポイント |
|---|---|
| ポスター/チラシ | 地域施設・館内掲示板などへ設置/視覚的訴求を強調 |
| SNS投稿 | 写真+体験イメージの動画/Instagramなど |
| 地域イベントサイト | ターゲット層が集まりやすいローカル掲示板や告知ポータル |
募集管理をラクにするツール
- Googleフォーム:無料&簡単、アンケート連携も可能
- イベント専用アプリ(Peatixなど):参加者管理、決済、リマインドまで一括管理
早期申し込みを促す工夫
- 早割(例:500円引き)
- 先着プレゼント(記念品、優先席)
3. 決済方法の設計
参加費を設定する場合は、ターゲット層に合った支払い方法の選定が鍵です。
代表的な支払い手段と特徴
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 現金払い(当日) | 誰でも使える/設備不要 | 紛失・釣銭ミスに注意 |
| 銀行振込 | 事前入金で安心 | 手間がかかる/未入金トラブルあり |
| PayPay・LINE Pay等 | 利用者多数/簡単 | 説明不足で使えない層がいる場合も |
| クレカ決済(Stripe等) | 手間なく導入可能 | 初期設定にやや手間あり/手数料発生 |
4. 当日の運営とトラブル対策
事前リハーサル・進行設計
- 時間配分やアナウンスの確認
- 紙芝居・ホワイトボードなど、視覚的に伝える工夫
- 子どもにとっての“待ち時間”対策(予備アクティビティなど)
準備しておきたい備品チェック
| カテゴリ | 内容例 |
|---|---|
| 道具 | ハサミ、のり、筆記具、予備材料など多めに用意 |
| 安全用品 | 救急セット、除菌スプレー、マスク・手袋など |
| 環境・会場管理 | ゴミ箱、ウェットティッシュ、案内サイン、名札など |
役割分担と運営体制
- スタッフごとに明確な役割を割り振る(受付/誘導/進行/安全管理)
- 子どもの年齢・スキルに応じて柔軟に声かけ・補助を行う
- 緊急連絡体制(スタッフ間の連絡手段/医療機関連絡先)を事前共有
よくあるトラブルと対応策まとめ
| 想定される課題 | 対応策 |
|---|---|
| 材料が不足してしまった | 予備を+10〜20%準備しておく |
| 進行が早すぎる・遅れる | 予備コンテンツ/短縮版を用意 |
| 子どもがケガ・迷子になる | 入退場管理、スタッフ配置、緊急連絡ルール徹底 |
| 雨天中止/荒天対応 | 屋内会場の確保/中止時の周知手段(メール、SNS) |
ワークショップ後のフォローアップで“次につなげる”
イベントは「やって終わり」ではありません。
ワークショップの価値を最大化し、次回の開催につなげるためには、終了後のフォローアップが非常に重要です。
参加者満足度の把握、改善点の洗い出し、リピート促進まで含めた対応が、企業や団体の信頼獲得・ブランド向上にもつながります。
1. 参加者アンケートで“生の声”を回収
イベント終了直後は、参加者の印象が新鮮なタイミング。
その場で簡単なアンケートを取るだけでも、次回の改善材料になります。
質問例(短時間で書ける形式)
- 一番楽しかったことは?
- もっとこうだったら良かった点は?
- 次に参加してみたいテーマはありますか?
2. 思い出を共有し“記憶に残す”
イベント後に「思い出が残る仕掛け」を用意することで、参加者の満足度はぐっと高まります。
SNS・ブログで写真を共有
- 当日の様子を写真付きで投稿(※顔出しは事前許可必須)
- 次回イベントの予告や、投稿者限定クーポンなども効果的
記念品や参加証の配布
- テーマに合わせたオリジナルシールやバッジ
- 制作物と一緒に持ち帰れるミニ賞状や参加証明カード
- 「参加ありがとう」カードをスタッフの手書きで添えると好印象
- ものづくり系イベントならその作品自体が思い出として残る
3. 成功点と課題を整理する
次回イベントのクオリティを高めるために、反省点と良かった点を明文化しておくことが大切です。
具体例
- 材料が不足 → 予備を+10%用意する
- 時間が押した → スタッフ数を1名増員
- 高評価だった点 →「子どもが笑顔だった」「説明がわかりやすい」など
スタッフで情報を共有
- イベント後1〜2日以内に振り返りミーティング
- 担当者ごとに改善点を出し合い、ドキュメント化
4. 次回開催に向けた準備へ
アンケートや振り返りで得た情報をもとに、次回の企画を改善。
開催頻度が年1〜2回程度でも、「前回より良かった!」という実感が参加者のリピートや紹介につながります。
改善につながる取り組み例
- 事前予約フォームの改善(分かりやすいUIに)
- SNSの告知タイミングを見直す
- ワークショップ内容を年齢別に細分化
フォローアップは“信頼と次回集客”の起点
ワークショップのフォローアップを丁寧に行うことで、以下のような成果が期待できます。
- 参加者との信頼関係が深まる
- 口コミによる集客・紹介が生まれる
- 継続開催の土台が築ける
- 社内・クライアントからの評価アップにつながる
ワークショップ運営は“HOKET LAB”にお任せください

「やってみたいけど、準備が大変そう…」「どこから手をつけていいか分からない…」
そんなときは、子ども向けイベントのプロ集団「HOKET LAB」にご相談ください。
HOKET LABができること
企画から当日運営まで、ワークショップを“まるっと”サポート。
- オリジナルテーマの企画提案
- 材料や装飾などの準備・キット制作
- プロスタッフによる進行・安全管理
- オンライン開催や遠隔地対応も可能
活用シーンはこんなに幅広い
| 利用シーン | 内容 |
|---|---|
| 企業の福利厚生 | 社員のお子様向けイベントに最適 |
| 商業施設の集客 | 親子参加型イベントで来場促進 |
| 自治体・地域イベント | 子ども会・地域活動の体験プログラムに |
| カーディーラー・住宅展示場 | 親子で楽しめるワークショップを併設し滞在促進 |
| イベントブースでの集客 | 賑わいを生み出し来場者の足を止めるきっかけに |
HOKET LABが選ばれる理由
- 子ども向けに特化した専門性
- 参加者の年齢や会場規模に応じた柔軟な提案力
- オンライン相談・柔軟なカスタマイズもOK
ざっくりした相談でももちろんOK!目的やご予算に応じて、最適な内容をご提案します。
まとめ|子どもたちが笑顔になるイベントを、安心・安全に
子ども向けワークショップは、アイデアと準備さえ整えば、初心者でも成功可能な企画です。
さらに、HOKET LABのような外部サービスを上手に活用すれば、運営負担を大幅に軽減しながら、高品質で記憶に残るイベントを提供できます。
ぜひ、この記事をヒントに、参加者の笑顔あふれるワークショップを企画してみてください!